会社を経営するうえで、役員報酬の設定額は、節税、社会保険料の負担、そして会社の財務状況に大きく影響する重要なポイントです。特に、これから法人化を検討していたり、マイクロ法人の運用を始めたばかりの方にとっては、「どのように金額を決めればいいか」「社会保険料とのバランスをどう取るか」といった疑問を抱えるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、役員報酬の基本的な仕組みから、実務上の注意点、金額の決め方、節税との関係性まで、初心者にもわかりやすく解説します。

小島 美和(佐藤 みなと)
合同会社あすだち 代表
時間に追われすぎない穏やかな生活を送りたくて、会社員生活を卒業→起業。オンライン事務代行として活動中。節約と時短をこよなく愛しています。息子と2人暮らしのシングルマザー。
めんどうな事務作業や雑務に追われていませんか?
みなとのオンライン事務代行がおすすめです
一般的な事務業務だけでなく、経理業務、ホームページ編集、SNS運用まで幅広くご依頼いただけます。
「こんな業務、お願いしても大丈夫かな?」というようなことがありましたら、お気軽にご相談ください!
役員報酬とは?給与との違いを解説

役員報酬は、会社の取締役や代表取締役などの役員に対して支払われる報酬です。社員に支払う給与とは、性質も決め方も大きく異なります。
一般的に給与は、労働基準法に基づいて労働の対価として支払われます。これに対して、役員報酬は、会社経営の責任と成果に対して、株式会社や取締役会などの決議を経て支払われるものです。
役員報酬と給与の違い
| 役員報酬 | 給与 | |
| 対象者 | 取締役、代表取締役、監査役など | 一般社員、アルバイト、パートなど |
| 決定方法 | 株主総会や取締役会の決議により決定 | 労働契約に基づき会社が提示・合意 |
| 契約形態 | 委任契約 | 雇用契約 |
| 労働基準法の適用 | 原則として適用されない | 適用される |
| 支給タイミングの自由度 | 定期同額給与などの制限あり | 柔軟に変更可能 |
| 賞与・臨時手当の扱い | 原則として損金算入不可 | 原則として損金算入可能 |
| 税務上の扱い | 条件付きで損金算入可 | 損金算入可能 |
| 社会保険の加入義務 | 一定条件で加入義務あり | 原則として加入義務あり |
| 所得の区分 | 給与所得 | 給与所得 |
| 労災の適用 | 原則として適用外 | 適用あり |
このように、役員報酬は従業員の給与とは決め方や法的な取り扱いが異なるため、経営者としての立場で適切に理解し、積極的に設定することが求められます。
役員報酬の基本ルールと決め方

役員報酬は、税務上の取り扱いや法的ルールにのっとって設定しなければなりません。ルールを知らずに設定してしまうと、損金として認められなかったり、思わぬ税負担につながったりすることがあります。
ここでは、役員報酬に関する基本的なルールと、実務上の決め方について解説します。
その1:定期同額給与の原則を守ること
役員報酬は、「定期同額給与」として、毎月同じ金額を支給する必要があります。
これは、法人税法のルールで、役員報酬を損金(経費)に算入するための条件のひとつです。不定期に金額を変えた報酬は、損金として認められず、法人税の負担が重くなるリスクがあります。
その2:株主総会または取締役会での決議が必要
役員報酬の金額は、社長個人の判断では決められず、会社の意思決定機関による決議が必要です。
これは、会社法で定められた手続きであり、正当な決定プロセスを経ていない報酬は、法的に無効とされる可能性もあります。特に株式会社では、株主総会の承認が必要です。正当な手続きを踏むことで、報酬額の正当性と法的な有効性が担保されるでしょう。
その3:実態に見合った金額の設定
役員報酬は、業績や職務内容に見合った適正な水準で設定する必要があります。
著しく高額または低額な報酬は、「税務上、不相当な報酬」として否認される可能性があります。また、社会保険料の負担にも影響するため、業績、業務量、社会保険とのバランスを総合的に判断することが重要でしょう。
その4:社会保険料の負担の考慮
社会保険料の負担を踏まえたうえで、トータルの手取りや法人コストを見ながら報酬額を決めましょう。特に、役員報酬が8.8万円以上で社会保険の加入が生じるため、注意が必要です。
月額報酬を8万円に抑えれば、社会保険に加入しないで済むケースもありますが、年金や医療保険の保障が薄くなる点は検討材料と言えるでしょう。税金、保険料、手取りをシミュレーションしながら、最適な金額を見極めたいですね。
その5:業種・地域による相場を参考にする
自社の業種や地域における、一般的な「役員報酬水準」を参考にすることも有効です。同業他社と比べてあまりに乖離した報酬額は、税務署から不自然とみなされる要因になります。
たとえば、従業員3名のIT系スタートアップで、月額50万円の報酬を設定していれば違和感は少ないですが、同じ条件で月額150万円では過大と判断されるかもしれません。地域・業界の相場観を踏まえた報酬設計は、リスクを抑えるうえで有効でしょう。
節税と社会保険料の最適バランス
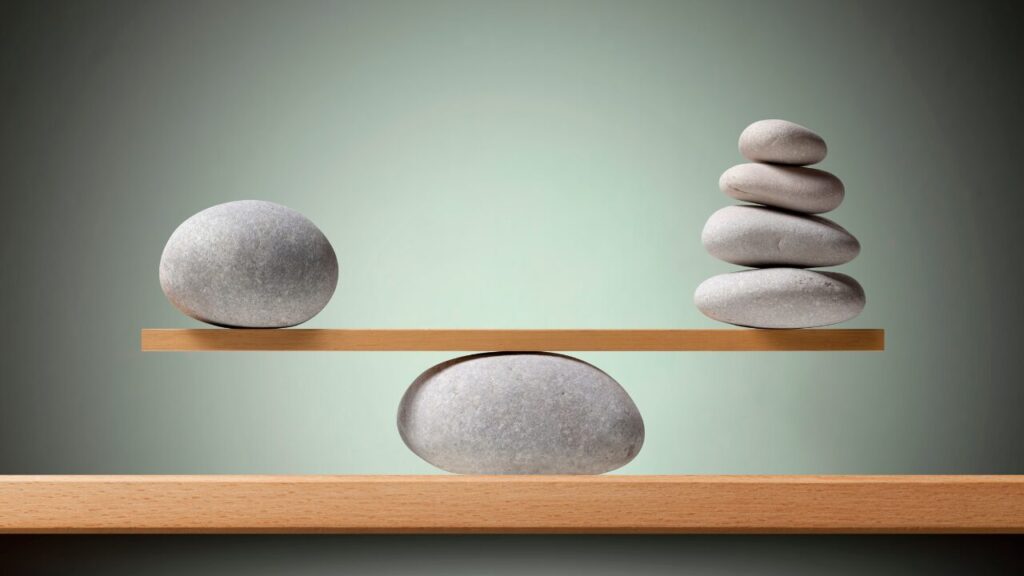
役員報酬の設定は、法人税の節税効果と社会保険料の負担を天秤にかけながら、トータルでもっとも合理的なバランスを目指すことが重要です。
役員報酬を高く設定すれば、会社の利益を圧縮できるため法人税の節税になりますが、そのぶん、個人の所得税、住民税、そして社会保険料が増加します。逆に、報酬を低く抑えれば社会保険料の負担は減りますが、法人に利益が残り、法人税が増える可能性があります。どちらに偏っても、全体としてのコストが高くなりかねません。
たとえば、役員報酬を月30万円に設定した場合、法人の利益は抑えられ、税引き前利益が減るため法人税の節税につながりますが、厚生年金や健康保険の保険料として、会社・個人合わせて年間100万円以上の負担が生じることもあります。そこで、報酬を月8万円〜10万円に抑えると、社会保険料の負担を軽減でき、結果として全体の資金効率が良くなるケースもあります。
最適な役員報酬は、「税金だけ」または「社会保険料だけ」を見て決めるのではなく、会社と個人を合わせた実質的な手取り・コストを総合的にシミュレーションしたうえで決定することが不可欠です。必要に応じて専門家と相談しながら、自社にとって最も合理的なラインを見極めましょう。
役員報酬のよくある失敗と注意点

役員報酬の設定には、税務や社会保険のルールが密接に関わっており、安易な判断で決めてしまうと、損金不算入や過剰な保険料負担など、思わぬトラブルにつながることがあります。特に初めて法人を設立した経営者や、マイクロ法人を運用している方にとっては、見落としやすいポイントも少なくありません。
ここでは、役員報酬に関してよくある失敗と注意すべき点をいくつかご紹介します。
注意点1:金額を途中で変更してしまう
期中で役員報酬の金額を変更すると、原則として損金に算入できなくなります。
法人税法では、定期同額給与が原則とされており、原則として毎月同じ金額で支給されていなければ、損金算入は認められません。業績の変動に応じて柔軟に報酬を変えることは、税務上、大きなリスクを伴います。
注意点2:議事録や決議書を残していない
役員報酬額が決まったら、その根拠となる議事録や決議書を作成、保管しておく必要があります。
税務調査では、報酬額が適切に決議されているかどうかが確認されるため、正式な手続きを証明できないと否認されるかもしれません。形式的な手続きも無視せず、社内文書の整備を徹底しましょう。
注意点3:社会保険の加入義務を見落とす
一定額以上の役員報酬を受け取ると、たとえ一人で経営する会社であっても、社会保険の加入義務が発生します。
法人の役員で、報酬が月8.8万円以上ある場合、原則として健康保険と厚生年金の加入が必要になります。これを怠ると、あとからさかのぼって徴収されることもあります。報酬額を決める際には、社会保険の加入要件を必ず確認しましょう。
ケース別の役員報酬の設計例

役員報酬の最適な金額は、法人の規模や目的、収益構造によって大きく異なります。「どのくらいの報酬が妥当なのか分からない」という方は、まず自社の立ち位置や目的に近いケースを参考にしてみましょう。
以下では、代表的な3つのケースごとに、実際の設計例を紹介します。
ケース1:年商1,000万円未満のマイクロ法人
目的: 社会保険料の負担を抑えつつ、節税メリットを活用したい
設計例: 月額役員報酬8万円(年96万円)
ポイント: 月額8.8万円未満にすることで、健康保険・厚生年金の加入義務を回避し、法人税・所得税を最小限に抑える設計です。生活費は個人事業収入や貯蓄など他の収入源で補完する形になります。
ケース2:節税を重視した中小法人(年商2,000〜5,000万円)
目的: 法人税と所得税のバランスを取りながら、手取りを最大化したい
設計例: 月額役員報酬30万円+年1回の事前確定届出賞与30万円
ポイント: 年間360万円の報酬で厚生年金の将来受給も確保しつつ、法人利益を圧縮して節税。賞与は「事前確定届出」をすれば損金算入可能となるため、計画的な運用がカギとなります。
ケース3:資産管理会社・副業収入の法人化
目的: 本業の給与と合わせて税率を抑える・社会保険の重複を避けたい
設計例: 役員報酬ゼロ〜月額5万円(年間報酬60万円以下)
ポイント: 本業で社会保険に加入している場合、副業法人の役員報酬は最低限またはゼロに抑え、所得分散と法人活用による節税を狙います。利益は法人に残し、将来の設備投資や経費処理に活用するケースも多いです。
まとめ

役員報酬の設計は、単なる「報酬額の決定」にとどまらず、法人税や所得税、社会保険料、そして会社の資金繰りにまで影響する重要な経営判断のひとつです。定期同額給与の原則や手続きの正当性を押さえることはもちろん、業績とのバランスや相場感、社会保険料との兼ね合いまで考慮して、全体最適な金額を決めることが求められます。
一人で判断するのが難しい場合は、必ず税理士や社労士などの専門家に相談し、自社にとってベストな報酬戦略を組み立てることをおすすめします。適切な役員報酬の設計は、会社の健全な成長と経営者自身の安心につながるでしょう。
みなとのオンライン事務代行がおすすめです

みなとのオンライン事務代行は、神奈川県横浜市を起点としたオンライン事務代行サービスです。
副業、個人事業主、一人社長、小規模事業者様にご利用いただいております。もちろん、中小企業経営者の方からのご依頼も大歓迎です。
初回のご相談は、オンラインにて無料で承っております。「こんな業務をお願いしたいんだけど、依頼できる?」といったご相談も承れますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。










コメント