「マイクロ法人と個人事業主の両方を使い分ける”二刀流”ってアリなの?」と疑問を抱えている方は少なくありません。すでに個人事業主として活動している人にとっては、「法人化=全事業を法人に移す」という選択を不安に感じるかもしれません。
そこでこの記事では、「マイクロ法人と個人事業主を使い分ける二刀流は本当に可能なのか?」「どんなメリット・デメリットがあるのか?」といった実務的な疑問に答えながら、向いている人の特徴や成功のポイントまでをわかりやすく解説します。

小島 美和(佐藤 みなと)
合同会社あすだち 代表
事務歴15年以上。2021年に独立、幅広い業種の一人社長や個人事業主のサポートをしています。「仕事のていねいさ」「相談しやすさ」に定評。
限られた時間の中で最大の成果を出す「効率化」を重視し、お客様が本来の業務に集中できるよう、心強いパートナーとして伴走します。
本業に集中したい一人社長・個人事業主のあなたへ
事務作業・雑務を手放して、自由な時間を増やしませんか?
みなとのオンライン事務代行の概要は[こちら]からご覧いただけます
マイクロ法人+個人事業主の「二刀流」は可能か?

結論、マイクロ法人と個人事業主を同時に運営する「二刀流」は可能です。
なぜなら、法律上、法人と個人は「別の存在」として扱われるからです。同一人物が両方を運営していても、法人の収益と個人の収益が明確に分けられている場合には、同時運用が認められます。ただし、所得区分や経費の按分には注意が必要で、税務上のルールを守ることが前提です。
このように、制度上、「マイクロ法人+個人事業主」の二刀流はできるとされており、工夫次第では大きなメリットを生む運用方法です。ただし、実務上のリスクを避けるためにも、専門家に相談しながら正しく管理しましょう。
マイクロ法人+個人事業主の「二刀流」のメリットとデメリット

マイクロ法人と個人事業主の「二刀流」は、節税や事業の柔軟性を高める有効な手段となるでしょう。
なぜなら、法人と個人は別人格として扱われ、それぞれの強みを活かした収益管理ができるからです。法人では、役員報酬を低く抑えて社会保険料を軽減しつつ、個人事業でフットワークの軽い活動を継続するなど、リスク分散と税務最適化を図れます。
一方、二重の帳簿管理、確定申告や法人決算の手間、税理士費用などのコストが増える点はデメリットと言えるでしょう。税務署からの目が厳しくなる可能性もあるため、運用には注意が必要です。
マイクロ法人+個人事業主の「二刀流」のメリット
| 内容 | |
| 節税効果 | 所得を法人と個人に分散することで、所得税や住民税の負担を軽減できる |
| 社会保険料の最適化 | 法人の役員報酬を低く設定することで、厚生年金などの社会保険料を抑えられる |
| 事業の柔軟性 | 法人と個人で異なる事業を展開しやすく、収益源の分散やチャレンジが可能になる |
| 信用力の向上 | 法人名義の口座や契約によって、対外的な信頼感・取引の幅が広がる |
| 経費の最適化 | 法人経由で経費計上できる範囲が増え、税務上のコントロールがしやすくなる |
マイクロ法人+個人事業主の「二刀流」のデメリット
| 内容 | |
| 手間が増える | 法人と個人、2つの会計・帳簿・申告業務が必要となり、管理が煩雑になる |
| コスト増 | 税理士報酬や法人維持費(登記、社会保険、口座維持など)が追加でかかる |
| 税務リスク | 所得や経費の線引きが曖昧だと、税務署から否認・調査対象になるリスクがある |
| 社会保険の誤認 | 加入義務や保険料の算定ミスなど、実務での取り扱いに誤解が生じやすい |
| 向き不向きがある | 所得が少ない人には逆に負担が大きくなり、かえって非効率になる可能性がある |
マイクロ法人+個人事業主の「二刀流」に向いている人の特徴

マイクロ法人と個人事業主の「二刀流」に向いているのは、
- 年間の所得が400万円以上ある
- 節税や社会保険料の最適化を本気で考えている
- 法人と個人で異なる事業を明確に分けて展開したい
- 記帳や税務の管理が苦にならない(または外注できる)
- 税理士に相談する習慣がある、または顧問契約をしている
人です。
その理由は、二刀流には節税や社会保険料対策といったメリットがある一方で、会計、税務、法務の管理が複雑になるためです。制度の理解と手間をかける意識がないと、かえってコスト増やトラブルの原因になりかねません。
上記の条件に自分が当てはまるか、冷静に見極めることが成功のカギとなるでしょう。
「二刀流」を成功させるポイントと注意点

マイクロ法人と個人事業主の「二刀流」を成功させるためには、正しい知識と慎重な運用が欠かせません。なぜなら、うまく活用できる場合には経済的メリットが大きいですが、間違った運用は税務署から指摘されたり、信用の失墜につながりかねないためです。
そこで、二刀流をうまく活用するために重要な実務上のポイントとよくある注意点について解説します。
「二刀流」を成功させるポイント
ポイント1:法人と個人で事業内容・収益源を明確に分ける
まずは、事業内容や収入源をハッキリ分けましょう。
法人と個人の活動が曖昧だと、税務署から「実質的には同一事業」と判断され、法人と個人を分ける意義が失われるリスクがあります。場合によっては、節税効果が否認されるかもしれません。
ポイント2:帳簿・口座・経費処理を完全に分離する
次に、帳簿、銀行口座、経費の処理は、完全に分けて運用することが必須です。
法人と個人は、税務上も別の事業体として扱われます。資金や経費の混同があると、「名ばかり法人」や「仮装隠ぺい」と見なされるリスクにさらされかねません。これは、税務調査で問題視されやすく、場合によっては追徴課税につながるおそれもあります。
ポイント3:定期的に税理士や専門家のチェックを受ける
マイクロ法人と個人事業主の二刀流を安全に運用するためには、定期的に税理士や専門家のチェックを受けましょう。
法人と個人を同時に運営する場合、税務、社会保険、法務のいずれも複雑になりやすく、自己判断で進めると制度違反や申告ミスにつながるかもしれません。特に、税制は毎年改正されるため、最新情報に基づいた対応が求められます。
「二刀流」を成功させる注意点
注意点1:同一事業と見なされるリスクへの対策
マイクロ法人の事業と個人事業主の事業が、「同一事業」と税務署に見なされないよう、明確な区分を意識しましょう。
法人と個人の事業内容があいまいで似通っていると、「実態は一体の事業」と判断され、節税のための分散と見なされかねません。その場合、法人と個人を分けていたこと自体が否認され、過少申告加算税(*)や追徴課税の対象となることもあります。
過少申告加算税は、申告した税額が実際より少なかった場合に課されるペナルティです。税務署からの指摘により修正申告をした際に、追加で納める税額の10~15%が加算されます。
注意点2:社保・税務の法改正に追いつくための情報収集体制
マイクロ法人と個人事業主の二刀流を継続的に運用するためには、社会保険や税制の法改正に対応できる情報収集が欠かせません。
税制や社会保険制度は毎年のように見直されています。最新のルールを把握していないと、気づかないうちに違法行為や不利益な申告になってしまうかもしれません。特に、社会保険の加入義務や役員報酬に関する基準は微妙な変更点が多く、見逃すと大きな影響を受けやすいです。
注意点3:維持コストと節税効果のバランスを定期的に見直す
マイクロ法人と個人事業主の二刀流を続けるうえで重要なことは、節税効果と維持コストのバランスの定期的な見直しです。
法人を維持するためには、登記費用、税理士報酬、社会保険料などの固定コストがかかり、節税額よりコストが上回る本末転倒な状況になる場合もあります。事業の成長や所得の変化に応じて、どちらの比重を高めるかの見直しが必要になるかもしれません。
失敗しないための「二刀流」チェックリスト

マイクロ法人と個人事業主の「二刀流」は、節税や事業拡大に有効な手段ですが、運用を誤ると手間やコストが増えるリスクもあります。
そこで、自分に向いているか、正しく管理できるかを見極めるために、事前にセルフチェックをして失敗を防ぐポイントを確認しましょう。
- 年間の所得が400万円以上ある
- 法人と個人で事業内容・収益源を明確に分けている
- 帳簿、銀行口座、経費処理を完全に分離している
- 税理士や専門家に相談できる体制がある
- 維持コストと節税効果のバランスを定期的に見直している
- 社会保険や税務の法改正にアンテナを張っている
- 法人と個人で使う名義、印鑑、請求書を使い分けている
- クラウド会計ソフトなどで記帳・管理の効率化を図っている
- 必要に応じて、将来的に一本化、法人化する選択肢も視野に入れている
- 名ばかり法人、形だけの節税になっていないか自問できる
まとめ
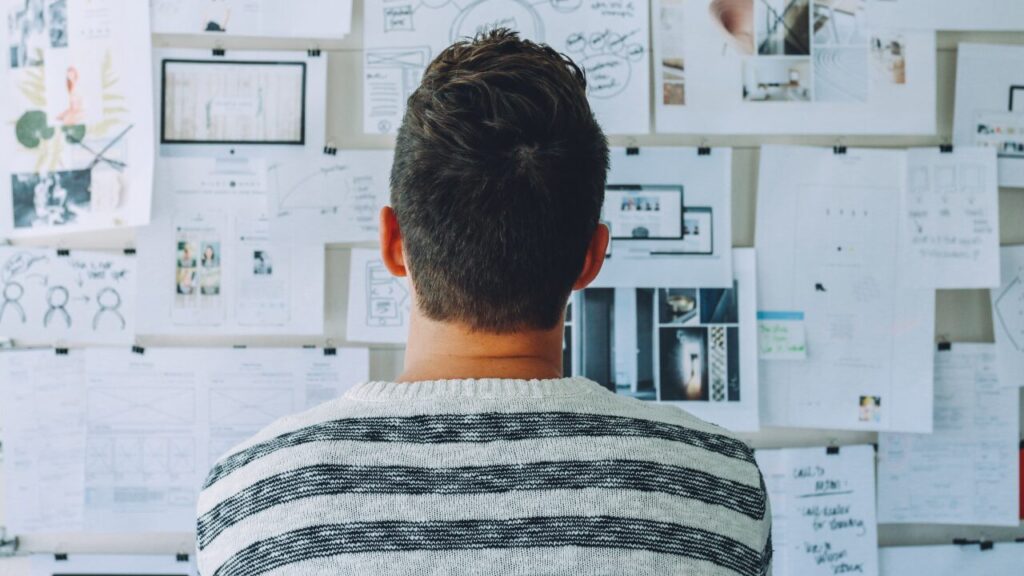
マイクロ法人と個人事業主を併用する「二刀流」は、節税、社会保険料の最適化、事業の柔軟な展開など、多くのメリットをもたらします。しかし一方で、帳簿や口座の管理、税務上の線引き、維持コストといった課題も伴います。
この運用を成功させるカギは、「法人と個人を明確に分けること」「正しい知識をもとに判断すること」「専門家と連携して管理を行うこと」の3点に尽きます。そして何より、節税効果だけでなく、長期的に見て本当に自分の事業にとって有益かどうかを、定期的に見直す姿勢が大切です。
「二刀流」は、正しく活用すれば自由度の高い働き方を実現できる強力な選択肢です。自分のスタイルや目指す方向に合わせて、慎重に導入を検討してみてくださいね。
一人社長・個人事業主の「やりたい!」を事務の力で支えます

「あれもこれもやらなきゃ…」毎日、そんな小さな事務作業に追われて、本来の仕事や大切な時間が削られていませんか?
みなとのオンライン事務代行では、事務歴15年以上の経験を活かし、あなたの「事務」「雑務」を丸ごとサポートします。単なる代行ではなく、あなたの大切なビジネスややりたいことをかなえるためのパートナーとして、心を込めて整えます。
「こんなこと、頼んでもいいのかな?」という小さなお悩みも、スッキリ解消しませんか?あなたのお話を聞けるのを楽しみにしています。
\ 30分間、Zoomでじっくりお話をうかがいます /









