個人事業主は自由に働ける半面、収入と労働時間が直結しやすく、仕事と生活の境界があいまいになりやすいです。その結果、長時間労働、孤独感、自己管理の難しさなど、ワークライフバランスを崩しやすい課題に直面しがちです。
そこでこの記事では、個人事業主が抱えるワークライフバランスの課題、メリット・デメリット、改善の具体策を整理し、横浜市で利用できる支援制度も紹介します。

小島 美和(佐藤 みなと)
合同会社あすだち 代表
時間に追われすぎない穏やかな生活を送りたくて、会社員生活を卒業→起業。オンライン事務代行として活動中。節約と時短をこよなく愛しています。息子と2人暮らしのシングルマザー。
めんどうな事務作業や雑務に追われていませんか?
みなとのオンライン事務代行がおすすめです
一般的な事務業務だけでなく、経理業務、ホームページ編集、SNS運用まで幅広くご依頼いただけます。
「こんな業務、お願いしても大丈夫かな?」というようなことがありましたら、お気軽にご相談ください!
個人事業主が直面するワークライフバランスの課題

個人事業主は自由に働けますが、稼働すればするほど収入が上がるため、自己管理の難しさに直面するケースが少なくありません。
ここでは、代表的な課題を整理していきます。
その1:収入と労働時間のトレードオフ
1つ目は、収入と労働時間が密接に結びついていることです。
会社員と違い、固定給が保障されていないため、働いた時間や案件数がそのまま収入に直結します。業態によっては、取引先の都合や納期に合わせた稼働が必要となる場合もあります。そのため、「休めば収入が減る」「働けば働くほど生活が安定する」というシンプルな構造になり、長時間労働になりやすいです。
その2:仕事とプライベートの境界があいまい
2つ目は、仕事とプライベートの境界があいまいになりやすいことです。
業態によって違いはありますが、自宅を仕事場としている場合、明確に勤務時間と休息時間を分けることが難しいです。気づけば深夜までパソコンに向かっていたり、休日も仕事のことを考えてしまうこともあるでしょう。心身はもちろん、脳も十分な休息を取りづらい状況になりやすいです。
その3:孤独感と自己管理の難しさ
3つ目は、孤独感や自己管理の難しさに直面することです。
会社員とは違い、一人で業務を抱えるケースが多く、精神的なプレッシャーを感じやすい環境です。また、働く時間や仕事量を決めるのは自分の采配になるので、体調やメンタルのコントロールがより重要になっていきます。
ワークライフバランスを整えるメリット・デメリット

ワークライフバランスを整えるメリットとデメリットは以下の通りです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 健康やメンタルが安定し、長期的に働きやすい 家族や友人との時間を確保でき、人間関係が充実する 休養によってリフレッシュし、生産性や発想力が向上する プライベートの満足度が高まり、仕事へのモチベーション維持につながる | 働く時間が減り、収入が減る可能性がある クライアントの要望に十分に応えられず、機会損失になるおそれがある 事業が安定していない段階では「売上優先」とのジレンマに直面する 自分で境界線を設定しないと、逆にバランスが崩れるリスクがある |
収入のために身を粉にして働いても、心身が疲れ果てて長期休養を取らざるを得ない状況になってしまっては元も子もありません。生活のために収入は不可欠ですが、長く働き続けるためにもワークライフバランスを整えることがおすすめです。
ワークライフバランスの実践的な改善方法
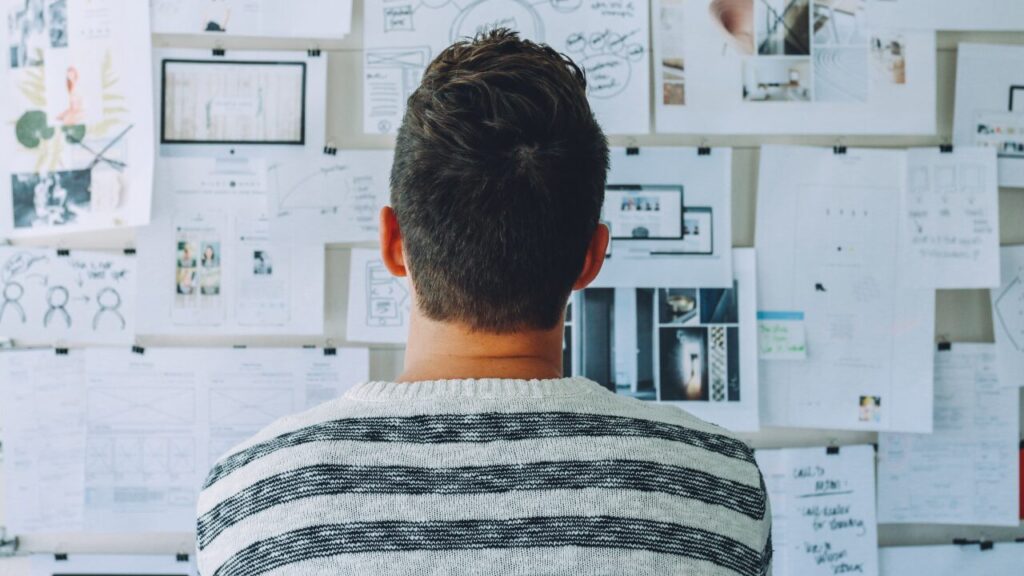
ワークライフバランスを整えるには、日々の働き方に小さな工夫を取り入れることが大切です。自由度の高い働き方だからこそ、臨機応変に対応できる仕組みづくりが大切です。
ワークライフバランスの実践的な改善方法は以下のとおりです。
方法1:事業の成長状況にあわせて働き方を調整する
まずは、事業の成長状況にあわせて働き方を調整することです。
創業したての場合、売上を作ることが至上命題になると言っても過言ではありません。この段階でワークバランスを取り入れて資金難になるくらいなら、割り切って事業に全エネルギーを注ぐのはひとつの選択肢になります。事業が成長し、売上が立って生活できるようになったタイミングで、ようやくワークライフバランスを整えてみる方法です。
個人的に、20代~30代の頃は、いわゆる「がむしゃら」に時間を忘れてできていた仕事でも、40代に入って「無理がきかない状態」になってきたことを痛感しています。世代によって「できること」「できないこと」が変わるので、できるうちに全力で取り組むことが一概に悪いというわけでもありません。
方法2:休養と休日をスケジュールに入れて確保する
次に、休養と休日をスケジュールに入れて確保することです。
休むことも仕事の一部ととらえ、スケジュールに休日を組み込む方法です。あらかじめ強制的にスケジュールをブロックすることで、時間を確保しやすくなります。趣味、運動、子供と過ごすなどでリフレッシュすることで、新しいアイデアがひらめき、体力回復にもつながるでしょう。
事業につながるための自己投資をすることも検討できるでしょう。読書、セミナー参加、ジャーナリングなどで現状を棚卸ししたり、スキルアップを図るのもおすすめです。
方法3:タイムマネジメントを徹底する
また、タイムマネジメントを徹底することもおすすめです。
ワークライフバランスを保つためには、時間の区切りを明確にすることがおすすめです。上記に挙げた休日だけでなく、子供を保育園に送り迎えする時間、昼食時間など必要な時間をあらかじめブロックしたうえで、残った時間のスケジューリングをします。作業時間に条件を設けることで、働きすぎを防げます。
方法4:タスク管理をしてシングルタスクで取り組む
スケジュールで稼働時間を確認したうえで、その日にやるべきタスクを箇条書きで書き出し、優先順位をつけて対応していきます。その際、複数のタスクを同時進行する「マルチタスク」ではなく、ひとつずつタスクを消化する「シングルタスク」がおすすめです。
稼働時間とタスク量が確定すれば、あとは限られた時間内でどのように全タスクを完了させるのかが腕の見せどころです。納品日やタスクの難易度を考慮してタスクの順位づけをして、ひとつずつタスクを実行すると、短時間で集中する仕組みが作れるので、集中力が持続しやすくなります。
方法5:業務を整理して外注を取り入れる
自分でなくてもできる業務は、思い切って外注するのも選択肢のひとつになるでしょう。
経理や事務作業は、事務代行やクラウドワークスを利用すれば、自分の時間を本業やプライベートに充てやすくなります。自分一人ですべてを抱え込まずに済み、やるべき仕事に集中できる環境を整えやすくなります。事業規模や売上によっては、検討してみてはいかがでしょうか。
- 終業時間を決めて、時間外は仕事をしない
- 優先順位を決め、やらなくてもいい仕事は手放す
- 自宅と仕事スペースを分ける、カフェやコワーキングスペースを活用する
- 仕事後に、散歩や読書など、気持ちをリセットする行動を取る
- 睡眠時間を優先し、昼休憩や運動を意識的に取り入れる
- 休日や夜間はSNSやメールの確認を控える
ワークライフバランスのために利用できる制度や支援策【横浜市】

横浜市では、個人事業主が働きやすい環境を作るための支援制度が充実しています。
ギリギリまで自力で何とかしようとしてもがくくらいなら、あらかじめ調べて支援制度に頼ってみるのもひとつの選択肢になるでしょう。たとえば以下のとおりです。
その1:創業おうえん資金(横浜市中小企業金融制度)
「創業おうえん資金」は、創業後5年未満の中小企業や個人事業主の創業を支援するために設けられた融資制度です。開業したばかりの方、これから事業を始める方が対象で、通常の金融機関からの融資に比べて、低い利率、保証料の軽減、原則無担保といった優遇が受けられるのが特徴です。
融資額は最大3,500万円、固定金利1.9%以内、担保や連帯保証人は原則不要です。横浜市による保証料率の女性により、保証料率が0.3%なので、資金調達をしてから事業展開を図るには選択肢のひとつになるでしょう。
その2:スタートアップおうえん資金
「スタートアップおうえん資金」は、創業支援プログラムを受けた事業者に対して、より有利な条件で資金調達ができる制度です。
通常の創業融資は審査が厳しいですが、この制度は横浜市の創業支援を受けた実績があることで、金融機関や保証協会からの信用度が高まり、金利や保証料の優遇を受けやすくなります。つまり、支援を受けて準備した事業者ほど、スムーズに資金を確保できる仕組みです。
その3:IDEC横浜(公益法人 横浜企業支援財団)による専門家出張相談
IDEC横浜が提供する「専門家出張相談」は、個人事業主が抱える経営や働き方の課題を、専門家が現場に出向いて直接サポートしてくれる心強い制度です。
経営、営業、会計、労務など幅広い業務を一人で抱えこみやすい個人事業主は、孤独や負担を感じやすい立場です。そこで、専門知識を持つアドバイザーが事業所を訪問し、課題を整理しながら具体的な改善策を提案してくれることで、効率化やワークライフバランスの向上につなげられるでしょう。
相談は事業所またはIDEC横浜の事務所内で行われます。経営全般の相談ができる「エキスパート面談」と商品やホームページなどのデザインについて相談ができる「デザイン面談」の2種類があり、どちらも年度内は初回から数回無料ですが、回数を重ねると1回あたり12,520円の費用がかかります。
その4:よこはまグッドバランス企業の認定
「よこはまグッドバランス企業認定」は、ワークライフバランスや多様な働き方を推進する企業と認める制度で、働きやすい環境づくりの目標や指標として活用できます。
認定を受けるためには、労働時間の適正化、子育て・介護との両立支援、女性活躍や多様性への配慮など、具体的な取り組みが求められます。つまり、単なる宣言ではなく、制度や実践を通して働き方改革に取り組む必要があります。これにより、従業員の定着率やモチベーション向上につながり、事業の信頼性も高まるでしょう。
なお、認定には、応募期間中の応募と審査を経て決定されます。PDF化された就業規則を提出する必要があるので、個人事業主や一人社長のように一人で事業運営をしている場合には、準備に時間を要するかもしれません。
その5:横浜健康経営認証
「横浜健康経営認証」は、従業員の健康づくりを経営課題と位置づけ、積極的に取り組む事業所を横浜市が認定する制度です。健康を基盤とした経営は、ワークライフバランスを整える重要な要素となります。
はたらく人の心身の健康が守られていなければ、長時間労働やストレスによって生産性が低下し、事業の継続性にも悪影響を及ぼしかねません。認証を受ける過程で、定期健診の徹底、メンタルヘルス支援、柔軟な勤務制度の導入などを実践するため、自然と健康を大切にするはたらき方が事業に根付いていくでしょう。
その6:脱炭素取組宣言制度
横浜市の「脱炭素取組宣言制度」は、事業者が環境負荷を減らすための姿勢を示す制度で、個人事業主にとっても信頼性の向上と経営コスト削減の両立に役立ちます。
この制度に参加すると、自社の「脱炭素化への取り組み」を横浜市が公式に認知・公表してくれます。さらに、省エネ診断のサポートや補助金・助成金の情報提供が受けられるため、実際に省エネ設備を導入する際の負担を軽減できます。環境対応をアピールできることで、顧客や取引先からの評価が高まる点も大きなメリットでしょう。
その7:横浜子育てサポートシステム
「横浜子育てサポートシステム」は、子育て中の親が安心して仕事や学業を続けられるように、地域の協力会員が一時的に子供を預かる仕組みです。
個人事業主は勤務時間を自分で調整できる一方、打ち合わせ、外出、納期対応などで子供の預け先に困るケースが少なくありません。この制度を利用すれば、地域の信頼できる協力会員に子供を預けることができ、必要な時に柔軟にサポートを受けられます。費用も安価に設定されているため、経済的な負担が少ない点も魅力でしょう。
ワークライフバランスを長期的に保つための心構え

ワークライフバランスは、事業の成長や家庭環境の変化に応じて、継続的に見直す必要がありません。特に、個人事業主は収入や仕事量が変動しやすいため、日々の働き方に柔軟さを持つことが欠かせないでしょう。
ここからは、長期的にバランスを維持するために意識すべき具体的なポイントを見ていきましょう。
その1:完璧を求めすぎない
まずは、仕事も生活も「完璧にこなそう」と思いすぎないことです。
すべてを完璧にしようとすると、時間もエネルギーも限界を超えてしまい、心身の疲労やストレスを溜め込みやすくなります。特に、個人事業主は一人で多くの役割を担うため、無理に理想を追求すると継続が難しくなります。
その2:健康を優先的に考える
次に、自分自身の健康を最優先にすることです。
心身の健康を損なえば、どれだけ仕事が順調でも継続できません。特に、個人事業主は自分が働けなくなると収入が途絶えるため、健康管理がそのまま事業継続に直結します。自分の生活を守るだけでなく、事業を継続させるためにも効果的な自己投資と言えるでしょう。
その3:定期的に振り替える習慣を持つ
最後に、定期的に自分の働き方や生活を振り返ることです。
個人事業主は、事業内容、収入、家庭環境の変化に大きく影響されます。そのため、一度整えた働き方も、年数を重ねて状況に合わなくなることがあります。定期的に振り返ることで無理が生じていないかを確認し、必要に応じて調整することができるでしょう。
まとめ

個人事業主にとって、ワークライフバランスは事業の継続性と生活の充実を両立するために欠かせないテーマです。完璧を求めすぎず、健康を最優先に考えて、自分に合う働き方を見つけたいものです。
ワークライフバランスは一度整えれば終わりではなく、ライフステージや事業環境に合わせて柔軟に見直していくものです。小さな工夫と支援制度の活用で、自分らしい働き方と暮らし方を築いていきましょう。
みなとのオンライン事務代行がおすすめです

みなとのオンライン事務代行は、神奈川県横浜市を拠点としたオンライン事務代行サービスです。
副業、個人事業主、一人社長、小規模事業者様にご利用いただいております。もちろん、中小企業経営者の方からのご依頼も大歓迎です。
初回のご相談は、オンラインにて無料で承っております。「こんな業務をお願いしたいんだけど、依頼できる?」といったご相談も承れますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。










コメント