小規模事業者、一人社長、個人事業主にとって、事務作業を誰に任せるかは大きな課題です。その中で、採用すべきか事務代行に依頼すべきかの判断に悩む経営者は少なくありません。
そこでこの記事では、事務代行を採用の代わりとして考えられる背景から、両者の契約やコストの違い、メリット・デメリットを整理し、それぞれが向いているケースをわかりやすく解説します。

小島 美和(佐藤 みなと)
合同会社あすだち 代表
事務歴15年以上。2021年に独立、幅広い業種の一人社長や個人事業主のサポートをしています。「仕事のていねいさ」「相談しやすさ」に定評。
限られた時間の中で最大の成果を出す「効率化」を重視し、お客様が本来の業務に集中できるよう、心強いパートナーとして伴走します。
本業に集中したい一人社長・個人事業主のあなたへ
事務作業・雑務を手放して、自由な時間を増やしませんか?
みなとのオンライン事務代行の概要は[こちら]からご覧いただけます
事務代行を採用の代わりと考えられる背景

事務代行は、人材採用にかかるコストやリスクを避けつつ、必要な事務作業をカバーできる手段として注目されています。
正社員やアルバイトを採用すると、給与や社会保険料といった固定費に加え、求人広告費、面接、教育の負担が発生します。さらに、採用した人材が短期間で離職してしまえば、再び採用活動が必要となり、時間もお金も二重に失われるリスクもあります。
たとえば、小規模事業者や一人社長の場合、フルタイムの事務を雇うほどの業務量がないこともあります。それでも経理処理、書類作成、スケジュール管理など定期的に発生する事務作業を対応するための手段として、事務代行は「採用の代わり」として有効な選択肢になるのではないでしょうか。
事務代行の契約と採用の違い
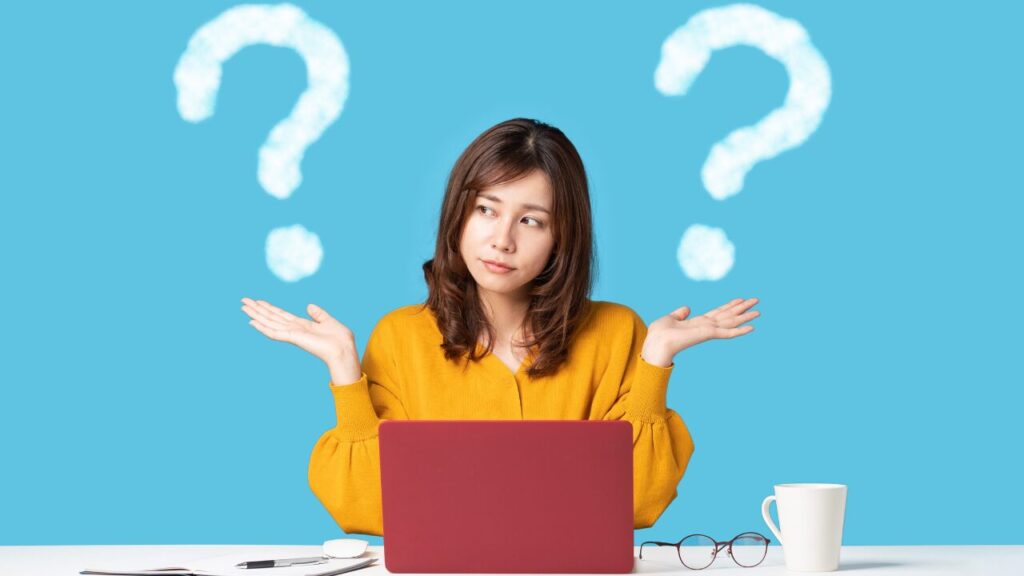
事務代行と人材採用は、いずれも業務を担う人を確保する手段ですが、その仕組みやコスト構造には大きな違いがあります。具体的には以下のとおりです。
| 項目 | 採用(正社員・アルバイト) | 事務代行 |
| 雇用形態 | 雇用契約 | 業務委託契約 |
| コスト | 給与+社会保険料+福利厚生 | 契約内容に応じた報酬のみ |
| 教育・研修 | 入社後に教育や研修が必要 | 即戦力として業務スタート可能 |
| 柔軟性 | 長期雇用が前提。人員削減が難しい | 短期・スポット利用が可能 |
| 業務範囲 | 幅広い業務を任せられる | 契約で定めた範囲に限定 |
| 責任の所在 | 社員として会社の管理下にある | 業務遂行は代行業者の責任 |
| ノウハウの蓄積 | 社内に蓄積されやすい | 車外にノウハウが残りやすい |
| 離職リスク | 退職や人員流出の可能性あり | 契約継続中は人員確保の心配が少ない |
違い1:契約形態
まずは契約形態です。
採用の場合は、正社員やアルバイトといった雇用契約を結び、会社側は給与の支払いだけでなく、社会保険料や福利厚生なども負担します。一方、事務代行は業務委託契約となり、成果物や稼働時間に応じて報酬を支払う形が一般的です。
そのため、固定費がかさみにくく、必要なときに必要なぶんだけを利用できます。
違い2:教育・育成コストの有無
次に、教育・育成コストの有無です。
採用した正社員やアルバイトには、業務に慣れるまで教育や研修が必要になるケースが多いです。その間も給与や指導にかかる人件費が発生し、場合によっては短期間でコストが無駄になるリスクもあります。
対する事務代行は、専門知識や経験を持つスタッフが業務を担当します。業務の引き継ぎやシステムなどの操作方法のレクチャーは必要でも、教育コストはほとんどかからないケースが多く、契約内容を伝えるだけで即戦力として動いてもらえるでしょう。
違い3:業務範囲や責任の所在
採用した社員は「会社の一因」として働くため、幅広い業務を柔軟に任せられます。そのぶん、会社が労務管理や成果に対して責任を負う必要があります。
一方、事務代行は、契約で定められた業務範囲に限定されます。成果物や進行に関する責任は代行業者側にあるため、依頼内容や守秘義務を明確にしておくことが重要です。
事務代行を採用の代わりにするメリット・デメリット

事務代行を採用の代わりに利用することで、企業は人材確保の負担を大きく軽減できるでしょう。
最大のメリットは、給与や社会保険料といった固定費を抱えずにすむ点です。必要な業務だけを切り出して依頼できるため、コストを変動費化でき、繁忙期やスポット業務にも柔軟に対応できます。また、教育や研修が不要で、即戦力として業務を任せられるのも強みです。
一方、デメリットもあります。業務範囲は契約内容に限定され、社員のように幅広い業務を任せることは難しいケースがあります。ただし、業務内容は長期契約になるほど変化していくものなので、契約時にざっくりと「事務全般」と定めておくことで、フレキシブルな対応をしてくれる事務代行業者もいます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 給与や社会保険料などの固定費が不要 必要な業務だけを依頼、コストを変動費化できる 教育・研修が不要で、即戦力を確保できる 繁忙期やスポット業務にも柔軟に対応可能 | 契約で定めた業務範囲でしか対応できないケースがある 社内にノウハウが蓄積されにくい 外注先とのコミュニケーションコストがかかる 社員のように幅広く柔軟に業務を任せづらい |
事務代行が向いているケース

事務代行は、すべての企業や個人事業主に一律で適しているわけではありません。採用と比べたときに、どのような状況で事務代行が力を発揮するのかを把握しておくことが重要です。
ここでは、特に事務代行の利用が効果的と言える代表なケースをご紹介します。
その1:業務量がフルタイム採用に満たない場合
日々の事務作業がある程度発生するものの、フルタイム社員を雇うほどの業務量がない場合には、事務代行の利用が適しています。
採用すると、業務量に関わらず給与や社会保険料などの固定費が発生します。一方、事務代行なら必要な作業だけを依頼でき、コストを変動費化できるため、ムダな人件費を抱えずに済みます。
たとえば、経理処理、請求書発行、データ入力などの事務作業が月に数十時間程度しかない企業や個人事業主の場合です。社員を採用すれば時間があまり、生産性が下がってしまいますが、事務代行なら必要なぶんだけを依頼できるため効率的でしょう。
その2:繁忙期やスポット対応が必要な場合
次に、繁忙期や一時的な業務量の増加に対応する場合です。
採用で人材を確保する場合、求人から教育まで時間とコストがかかり、短期間だけ必要な業務には不向きです。事務代行なら契約期間や依頼範囲を柔軟に調整できるため、必要なときだけ人手を増やせます。
たとえば、年度末の経理処理や決算業務、イベント開催に伴う資料作成など、短期的に業務が集中する場面です。社員だけでは対応しきれない作業も、事務代行の活用によって一時的にリソースを補えるため、本業に支障をきたさないで済むでしょう。
その3:専門知識が必要な業務を任せたい場合
また、専門的な知識やスキルを必要とする業務です。
採用した社員に新しいスキルを習得させるには教育コストや時間がかかり、短期的な業務には不向きです。一方、必要としているスキルを習得済の事務代行に依頼すれば、すぐに専門的な業務を進めてもらえるでしょう。
たとえば、SNS運用、Webサイトの更新、専門ソフトを使ったデータ管理です。社内で担当者をイチから育成すると負担が大きいですが、事務代行を活用すれば必要な部分だけをプロに依頼でき、成果も早く得られます。
その4:本業に集中したい経営者や個人事業主
最後に、本業に集中したい経営者や個人事業主です。
請求書発行、データ入力、スケジュール調整といった日々の事務作業は欠かせませんが、直接売上に結びつく業務ではありません。限られた時間と労力をこれらに取られてしまうと、本来注力すべき営業活動や企画立案に影響が出るかもしれません。
たとえば、一人社長が顧客対応や新規開拓に時間を割きたいときに、事務代行にバックオフィス業務を依頼すれば、本業に集中でき、事業全体のスピードを高めることが可能になります。「時間の確保」と「生産性向上」が期待できるでしょう。
採用が向いているケース

業務の性質や事業の将来像によっては、外注よりも自社で人材を採用した方が効果的な場合があります。
ここでは、事務代行では補いきれない部分や、長期的な視点で考えたときに採用が望ましいケースを紹介します。
その1:継続的かつ大量の業務がある場合
まずは、日常的に大量の事務作業が発生する場合です。
業務量がつねに多い状況では、外注を繰り返すよりも、人材を確保した方が長期的コストを抑えられるでしょう。社員であれば、臨機応変に業務を振り分けられる可能性もあります。
たとえば、毎日数十件以上の請求書、顧客対応、電話や来客の応対など、つねに一定以上の事務作業が発生する中小企業です。こうした場合は社員を採用して、社内に人材を確保する方が効率的に回せます。
その2:社内にノウハウを蓄積したい場合
次に、自社に業務知識やノウハウを長期的に残したい場合です。
事務代行は外部リソースを利用する仕組みのため、経験や知識は事務代行業者にとどまり、社内に蓄積されづらいです。一方、採用した社員であれば、業務を通じてスキルや経験が社内に蓄積され、将来の戦力として活かせるでしょう。
たとえば、自社独自の業務フローや特殊なシステムを扱う場合、長期的に働く社員が担当することでノウハウが蓄積され、業務効率や改善にもつながります。
その3:長期的な人材育成を重視したい場合
最後に、将来を見据えて長期的な人材を育成したい場合です。
事務代行は即戦力を提供するサービスですが、長期的な人材育成やキャリア形成間瀬は担えません。社員を採用すれば、業務経験を積ませながら専門スキルやマネジメント能力を伸ばし、将来的に中核人材として育てることが可能でしょう。
たとえば、成長過程にある企業で、将来の管理職候補や幹部人材を確保したい場合です。新人を採用して教育・研修を行うことで、会社の理念や文化を理解した人材を長期的に育てられます。
事務代行と採用を併用する選択肢

事務代行と採用のどちらか一方にするのではなく、両方を組み合わせて活用することで、効率性と柔軟性を高められます。ここでは、具体的な併用のケースをご紹介します。
その1:ルーティン業務は事務代行に任せる
まずは、定型的で繰り返し発生する業務を事務代行に任せる方法です。
ルーティン業務は重要ではあるものの、売上や事業成長には直結しにくいため、社員が対応すると時間や労力のコストが大きくなります。事務代行に外注すれば、社員はより付加価値の高い業務に集中できるでしょう。
たとえば、請求書の発行、経費精算、データ入力、郵送物の管理などです。これらは正確性が求められる一方で、専門スキルがなくても対応できる業務のため、事務代行に切り出すことで効率化も図れるでしょう。
その2:繁忙期や一時的な業務増加に対応する
次に、繁忙期や一時的に業務量が急増するタイミングで、事務代行を活用する方法です。
採用で人員を確保しようとすると、求人から教育までに時間とコストがかかり、短期間の業務には対応しづらいからです。事務代行なら、必要な期間だけ依頼できるため、柔軟にリソースを調整できます。
たとえば、決算期に経理業務が集中する場合や、イベント準備で書類作成・発送業務が一時的に膨らむ場合です。社員だけで対応すると本業に支障が出ますが、事務代行を使えば負担を分散でき、業務の遅延も防げます。
その3:成長過程で段階的に採用を増やす
最後に、事業の成長段階で業務量の増加に応じて、事務代行から採用へ切り替える方法です。
創業期や小規模事業の段階で社員を雇うと、人件費の固定化によるコスト負担が大きくなります。一方、事務代行なら必要な業務だけを外注でき、コストを抑えながら柔軟に事業を運営できます。そして、業務が安定して増えてきた時点で採用に切り替えれば、ノウハウを社内に蓄積しやすくなるでしょう。
たとえば、起業初期は請求書発行や経理処理を事務代行に任せ、経営者は営業や企画に集中します。その後、事業拡大により毎日多くの事務業務が発生するようになった段階で、社員を採用して社内体制を強化するとスムーズです。
まとめ

事務代行と採用には、それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットがあります。
重要なのは、どちらか一方を選ぶのではなく、自社の業務量や将来の成長計画に合わせて最適な方法を検討することです。自社にとってどのスタイルが最適化を見極め、戦略的に選択していきましょう。
一人社長・個人事業主の「やりたい!」を事務の力で支えます

「あれもこれもやらなきゃ…」毎日、そんな小さな事務作業に追われて、本来の仕事や大切な時間が削られていませんか?
みなとのオンライン事務代行では、事務歴15年以上の経験を活かし、あなたの「事務」「雑務」を丸ごとサポートします。単なる代行ではなく、あなたの大切なビジネスややりたいことをかなえるためのパートナーとして、心を込めて整えます。
「こんなこと、頼んでもいいのかな?」という小さなお悩みも、スッキリ解消しませんか?あなたのお話を聞けるのを楽しみにしています。
\ 30分間、Zoomでじっくりお話をうかがいます /









