事務代行サービスの利用後に、受け取った請求書を見て「この支払いは何費にすればいい?」と迷う方は少なくありません。勘定科目を間違えると、経費の集計がずれたり、税務処理で修正が必要になったりすることもあります。
そこでこの記事では、事務代行費用の正しい勘定科目の選び方から、具体的な仕訳例、税務上の注意点、間違えないためのコツまでをわかりやすく解説します。

小島 美和(佐藤 みなと)
合同会社あすだち 代表
事務歴15年以上。2021年に独立、幅広い業種の一人社長や個人事業主のサポートをしています。「仕事のていねいさ」「相談しやすさ」に定評。
限られた時間の中で最大の成果を出す「効率化」を重視し、お客様が本来の業務に集中できるよう、心強いパートナーとして伴走します。
本業に集中したい一人社長・個人事業主のあなたへ
事務作業・雑務を手放して、自由な時間を増やしませんか?
みなとのオンライン事務代行の概要は[こちら]からご覧いただけます
事務代行とは?

事務代行は、起業や個人事業主が行う経理、総務、秘書業務などの事務作業を、外部の専門業者やフリーランスに委託するサービスのことです。業務内容は幅広く、請求書発行や経費精算、データ入力、スケジュール管理など、社内で行う事務全般をカバーできます。
この記事では勘定科目や仕訳の視点に絞って解説しているので、事務代行の具体的なサービス内容や選び方は別記事をご覧にて参考にしてくださいね。
事務代行費用の勘定科目はどうするのか
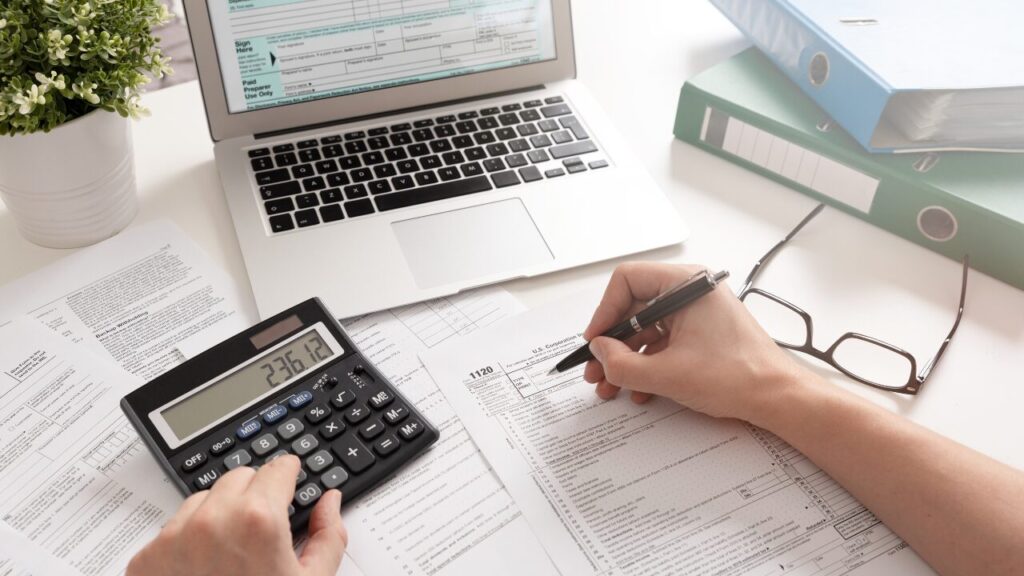
事務代行の費用は、業務内容や契約形態によって勘定科目の選び方が変わります。
一般的には「外注費」や「業務委託費」として計上するケースが多く、税務上も問題ない処理方法です。特定の業務に限定された依頼(経理入力や請求書発行など)であっても、継続的に委託している場合は同様の科目が適用されます。
ただし、事務代行の内容が単発の軽作業や事務用品の購入などを含む場合には、「雑費」や「消耗品」に振り分けた方が適切な場合があります。契約書や請求書に記載された業務範囲を確認し、実態に合った科目を選ぶことが大切です。
なお、法人と個人事業主で会計処理の呼び方や科目名が異なる場合もあるため、迷ったときは会計ソフトの推奨科目や税理士のアドバイスを参考にすると安心でしょう。
事務代行の仕訳例

事務代行費用の仕訳は、支払方法や契約条件によって微妙に異なります。
ここでは、代表的な3つのケースを紹介します。勘定科目は「外注費」や「業務委託費」を基本とし、契約内容に応じて変更する必要があります。
その1:銀行振込で支払った場合(即時支払い)
(借方)外注費 〇〇円 / (貸方)普通預金 〇〇円
その2:クレジットカードで支払った場合
(借方)外注費 〇〇円 / (貸方)未払金(カード会社名) 〇〇円
その3:請求書を月末締めで翌月支払う場合
(借方)外注費 〇〇円 / (貸方)未払金 〇〇円
なお、消費税課税事業者の場合は、借方の金額を「税込」で処理し、消費税区分を「課税仕入れ」として登録します。源泉徴収が必要な契約形態の場合は、支払額と経費計上額が異なるため、控除額を別途仕訳する必要があります。
税務上の注意点

事務代行費用を経費計上する際は、税務処理についていくつかの注意点があります。
注意点1:源泉徴収が必要な場合と不要な場合の違い
まずは「源泉徴収の有無」です。
契約が「業務委託契約」であり、かつ個人に支払う場合は、所得税の源泉徴収が必要なケースがあります。逆に、法人に支払う場合や源泉対象外の業務内容であれば、控除は不要です。
注意点2:消費税区分(課税/非課税/対象外)の判断
次に、消費税区分の設定です。
事務代行は原則として課税仕入れに該当しますが、免税事業者からの請求や源泉徴収対象の契約では、請求額や税額の計算方法が異なる場合があります。会計ソフトで登録する際は、必ず請求書を確認しましょう。
注意点3:経費計上時期(発生主義と現金主義)
最後に、経費計上のタイミングにも注意が必要です。
発生主義を採用している場合は、業務が完了した費や請求書発行日に計上します。現金主義の場合は、支払日ベースで処理します。契約書や社内の会計方針に沿って一貫性を保つことが、税務調査時のトラブル防止にもつながるでしょう。
事務代行費用の勘定科目を間違えないためのコツ

事務代行費用の勘定科目は、業務内容や契約条件によって変わるため、判断を誤ると仕訳のやり直しや税務調査時の指摘につながります。
そこで、次のポイントを押さえておくと安心です。
その1:契約書や請求書の業務内容を確認する
業務が経理や事務サポート全般であれば、「外注費」や「業務委託費」が適切ですが、単発の雑務や備品購入が含まれる場合には「雑費」「消耗品費」なども検討されるでしょう。
その2:会計ソフトの推奨科目を活用する
freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計では、取引内容に応じた科目候補が表示されます。これを参考にすれば、税務の一般的な処理に沿った仕訳が可能です。
その3:継続的に同じ科目を使う
同じ内容の支払いでも、月によって科目を変えてしまうと経費管理が煩雑になり、決算書の信頼性も下がります。初回に決めた科目を継続的に使うことが大切です。
その4:迷ったら税理士に確認する
判断が難しい場合には、税理士や会計事務所に相談して処理方針を明確にしておきましょう。後々に起こりうるトラブルを防げます。
まとめ

事務代行費用の勘定科目は、業務内容や契約条件によって変わりますが、原則は「外注費」または「業務委託費」を使うのが一般的です。契約書や請求書の記載内容を確認し、実態に合った科目を選ぶことが正確な経理処理につながります。
経理処理の判断に誤った場合は早めに税理士へ相談し、ルールを明確にしておくことで、決算や税務調査の場面でも安心して対応できるでしょう。
一人社長・個人事業主の「やりたい!」を事務の力で支えます

「あれもこれもやらなきゃ…」毎日、そんな小さな事務作業に追われて、本来の仕事や大切な時間が削られていませんか?
みなとのオンライン事務代行では、事務歴15年以上の経験を活かし、あなたの「事務」「雑務」を丸ごとサポートします。単なる代行ではなく、あなたの大切なビジネスややりたいことをかなえるためのパートナーとして、心を込めて整えます。
「こんなこと、頼んでもいいのかな?」という小さなお悩みも、スッキリ解消しませんか?あなたのお話を聞けるのを楽しみにしています。
\ 30分間、Zoomでじっくりお話をうかがいます /









